はじめに
確定拠出年金(iDeCo・企業型DC)は、積み立て時の情報は多い一方で、“受け取り方(出口戦略)”については意外と語られていません。
FIREやセミリタイアを考える人にとって、60歳以降の受け取り設計は老後資金計画の要です。本記事では、私まっつぁんの実際の設計をベースに、「年金形式・10年受け取り」による確定拠出年金の活用方法を解説していきます。
確定拠出年金の受け取り方法とは?
60歳以降、確定拠出年金(iDeCo・企業型DC)は以下の方法で受け取れます。
- 一時金(全額まとめて受け取り)
- 年金形式(5年〜20年で分割)
- 一時金+年金形式の併用(制限あり)
それぞれの特徴は以下の通りです。
一時金:退職所得扱い
- 退職所得控除が使える(が、退職金と重なると控除枠を超えるリスク)
- 課税所得が大きくなりやすく、税負担が重くなる可能性
年金形式:雑所得扱い
- 毎年少しずつ受け取る形
- 公的年金等控除+基礎控除を活用すれば、非課税も可能
- 一度設定すると原則変更不可
控除額の目安
- 60〜64歳:公的年金等控除60万円+基礎控除48万円 → 年108万円までは非課税(他に所得がない場合)
- 65歳以上:公的年金等控除110万円+基礎控除48万円 → 年158万円まで非課税
まっつぁんの受け取り戦略(リアル事例)
私の計画は以下の通りです。
- 55歳で退職し、退職所得控除は退職金で使い切る
- iDeCo・企業型DCは60〜69歳の10年で年金形式受給
- 年108万円以下に抑えて“非課税枠”を活用
- 公的年金は70歳から繰り下げ受給(約148.5万円→繰下げで約210.7万円)
この戦略により、
- 税負担を極小化
- 国保・介護保険料も抑制
- 投資資産の取り崩しタイミングを先送り可能
という3拍子が狙えます。
一時金 vs 年金形式:シミュレーション比較
ケース:1,080万円のiDeCoを受け取る
| 方式 | 税区分 | 税額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 一時金 | 退職所得 | 約134万円 | 控除枠なし、課税所得540万円 |
| 年金形式10年 | 雑所得 | 0円 | 年108万円×10年 → 非課税 |
※再投資元本にも影響あり。一時金は税引後946万円、年金形式なら1,080万円フル活用可。
国保・介護保険料の影響(大阪市モデル)
非課税世帯なら、以下の通り大幅に軽減されます。
| 年齢帯 | 年間保険料 | 内訳 |
| 60〜64歳 | 約35,100円 | 国民健康保険料のみ |
| 65〜69歳 | 約77,000円 | 国保+介護保険料(非課税第2段階) |
10年間の合計:約56万円
副業とのバランス:柔軟設計のすすめ
- 副業収入がある年:控除枠を少しオーバーしても税率は低く抑えられる(所得税5%、住民税10%)
- 副業がない年:控除枠内に抑えて“非課税化”
→ 年金形式は、毎年の状況に応じて調整可能な“柔軟性の高さ”が最大のメリットです。
受給前のアセット調整も忘れずに
- 運用が好調で評価額が上振れすると、非課税枠を超えるリスクあり
- 受給開始前に株式→債券や定期預金へスイッチングを
- 受給開始後は原則スイッチング不可なので、計画的に準備を
よくある誤解・注意点
- 一時金受給は退職金と合算されて課税ゾーン突入リスクあり
- 年金形式も雑所得扱いなので、副業やその他収入次第では課税の可能性
- 年金形式の金額は一度設定すると変更できない
- 金融機関によって最低金額・年数等の条件が異なる(例:SBI証券は年間12万円以上、5〜20年)
まとめ
- 確定拠出年金は“受け取り方”次第で税金と保険料に大きな差が出る
- 年金形式なら控除を活用して非課税化も可能。副業収入との相性も良い
- 上振れ対策として受給前のアセット配分見直しがカギ
少し設計が複雑に感じるかもしれませんが、しっかり準備すればかなり強力な老後資金戦略になります。FIREやセミリタイアを目指す方には、ぜひ“出口”にも注目してほしいところです。
ということで、
結局……めんどくさいわぁ。。。。。。
間違ってたらどなたかご教示くださいm(_ _)m

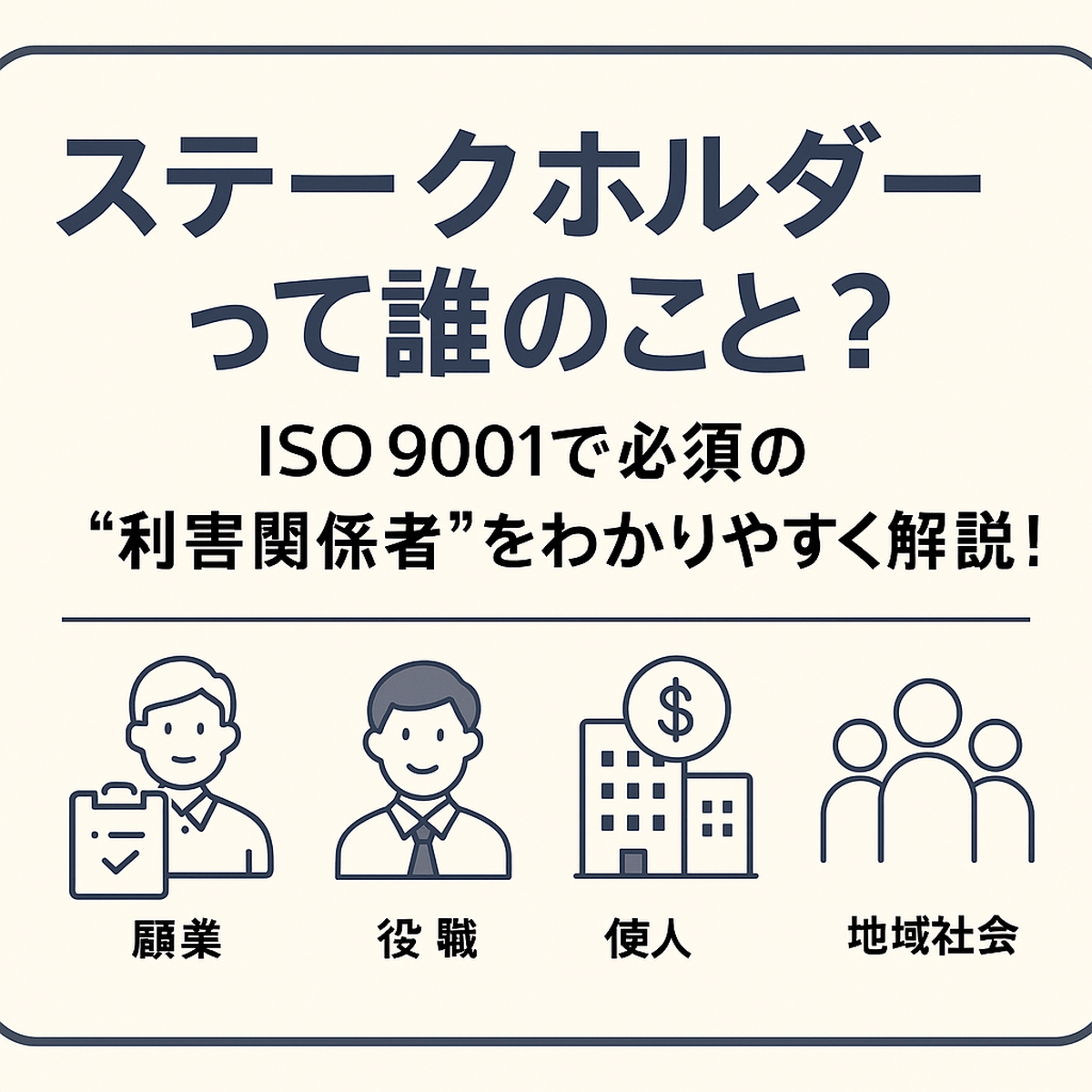

コメント