ISO9001を運用していると、必ずと言っていいほど直面するのが「不適合品」の問題です。 現場で「これ、どう処理したらいいの?」と迷った経験がある方も多いのではないでしょうか。 本記事では、不適合品の基本から、現場で迷わないための取り扱い・記録・その後の流れまで、監査やトラブルを未然に防ぐためのポイントを分かりやすく解説します。
「不適合品=面倒くさいもの」ではなく、実は組織全体の品質アップや業務改善にもつながる大事なテーマ。 この記事を読めば、ISO初心者でも明日から自信を持って対応できるようになります!
不適合品とは?(定義・目的)
不適合品とは、要求事項(仕様・基準・約束した品質など)を満たしていない製品やサービスのこと。 ISO9001では「不適合の管理」が明記されており、不適合が発生した場合は社内で明確に識別・隔離し、原因を明らかにした上で適切な処置を行う必要があります。
【目的】
- 不適合品の流出(顧客への出荷、次工程への渡し)を防ぐ
- 原因を明らかにして再発防止につなげる
- 品質マネジメントシステムの信頼性向上
不適合品の取り扱いフロー(STEP形式)
- 不適合の発見・報告
現場・検査担当・クレーム受付など、誰が気づいてもすぐに上司や担当者へ報告。 - 不適合品の識別・隔離
他の良品と区別できるよう、タグや専用エリアで識別。物理的に分けて混入を防止。 - 記録の作成
不適合発生の内容・発生日時・数量・原因(分かる範囲)・担当者を記録(不適合品管理表など)。 - 処置の検討・実施
- 補修・再加工できるか - 廃棄か - 特別採用(基準外でも顧客と合意のうえ使う)か
を現場責任者・品質管理担当と協議し決定。 - 処置後の記録・再確認
再加工した場合は再検査・再確認を行い、OKなら良品化、NGなら再度不適合品として管理。 - 原因調査・再発防止
一定量・重大な不適合は原因調査を行い、是正処置(仕組み・ルールの改善)まで検討。
よくあるミス・監査指摘(事例・対策)
- ミス事例1:識別タグを付け忘れ、良品と混ざった
→ 現場で識別徹底、隔離ルールを明文化 - ミス事例2:不適合発生記録があいまい・記載漏れ
→ 記録フォーマットを統一、記載漏れチェックリスト設置 - ミス事例3:原因不明のまま繰り返し発生
→ 一定件数・重大インシデントは必ず原因調査・報告会議 - 監査指摘例:「再発防止までできていない」「処置記録が残っていない」
→ 是正処置・再発防止の流れを業務マニュアルに反映し、運用まで徹底
ツール・フォーマット例
- 不適合品管理表(記録例)発生日製品名数量不適合内容処置担当者再発防止策2025/7/1A製品5個寸法不良再加工田中検査治具調整
- 識別タグサンプル
- 赤色タグ/「不適合」スタンプ
- 記入欄:品名、発生日、内容、処置
- 原因調査書・是正処置報告書
- 発生原因、対策、責任者、実施日
まとめ
- 不適合品は必ず「識別・隔離・記録」することが基本
- 処置後も再確認と記録を残し、流出防止を徹底
- 重大事例は原因調査・再発防止まで実施し、仕組み改善につなげる

まっつぁん
不適合品の管理は「めんどう」でも、現場の信頼と品質維持には欠かせません。
指摘やトラブルが起きる前に、シンプルなルール化と習慣付けが大切です。
次回予告
「PDCAサイクルの本当の回し方」を予定してます。


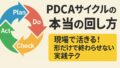
コメント